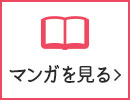当事務所では、いわゆる不倫の示談書の作成も承っております。
以前、当事務所が手掛けた不倫の示談書作成について、自称弁護士から当事務所宛に電話がありました。
曰く、「あなた(当事務所)は、示談書の作成にあたり、相手方に交渉したことがうかがえる。交渉は弁護士しかできないため、弁護士法違反(非弁行為)である。」という趣旨でした。
どうやら、当事務所の業務が非弁行為に該当することを主張したいようです。
ところが、自称弁護士の主張は、全くもって失当です。話になりません。
以下に私見を述べることにします。
1 弁護士法72条と法律事務
弁護士法72条では、「非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止」として、次のように記載されています。
「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」
つまり、弁護士以外の者は、報酬を得る目的で、法律事件を取り扱ってはならないということです。
逆に言えば、弁護士以外の者でも、「法律事件」に該当しない案件であれば、取り扱いが認められるということです。また、弁護士法以外に別段の定めがある場合は、取り扱いが認められます。
では、「法律事件」とは何でしょうか?
2 法律事件の定義
弁護士法による規制を受けるのは、法律事件に関する法律事務と言えますが、行政書士会は、これを「権利義務や事実関係に関して関係当事者間に法的主張の対立があり、制度的に訴訟などの法的紛争解決を必要とする案件」としています。
つまり、弁護士法の規制を受ける(非弁行為)となる事案は、法的主張の対立があり、解決のために訴訟等の手続が必要な事案であるといえます(事件性必要説)。
逆に言えば、法的主張の対立がなく、解決のために訴訟等の手続を要しないような案件は、弁護士法の規制を受ける法律事件に該当せず、非弁行為にあたらないことになります。
また、弁護士法を所管する法務省も、「「その他一般の法律事件」に該当するというためには、同条本文に列挙されている訴訟事件その他の具体的例示に準ずる程度に法律上の権利義務に争いがあり、あるいは疑義を有するものであることが要求される。」と解釈(令和4年11月11日法務省大臣官房司法法制部)しており、やはり、「法律事件に関する法律事務」というためには、「事件」と言えるほどの権利義務に対立があり、解決に裁判所等の手続を要するような事案でなければならないといえます。
3 当事務所の業務へのあてはめ
当事務所は、ご依頼者様から依頼を受け、示談書を作成したわけですが、実は、ご依頼者様と相手方は、当事務所への依頼前に、慰謝料を授受を目的とした合意がありました。
つまり、相手方は、自らの責任を認め、示談による解決に合意していたのです。
となると、示談による解決に合意がなされている以上、「権利義務や事実関係に関して関係当事者間に法的主張の対立」「訴訟事件その他の具体的例示に準ずる程度に法律上の権利義務に争いがあり、あるいは疑義を有するもの」はありません。当然、裁判所が関与する手続の必要性もなく、実質的に争い、すなわち事件性はなかったのです。
当事者間の争いがない以上、もはや法律事件ですらなく、弁護士法に違反することなど原理的にあり得ないのです。
4 相手方とのコミュニケーション
示談も一種の契約であり、当事者双方の意見の合致が必要です。当然、当事務所も両当事者に確認をとりながら示談書の作成を行わなければなりません。
では、相手方と対話や協議をすることが弁護士法が規制する「交渉」にあたるのでしょうか?
そんなはずはありません。
相手方も責任を認め、意見の対立がなく、争いも事件性もない以上、有利な条件を引き出す「交渉」の余地はありません。
事実、東京都行政書士会『行政書士必携~他士業との業際問題マニュアル~』でも、次のように記載されています。
Q7 行政書士が不倫問題を抱える一方の当事者から依頼され、不倫の相手方と慰謝料をめぐる示談交渉することは弁護士法72条に違反するのでしょうか?
A 相手方が不倫関係の事実を認め、不倫関係の解消に向けて合意する意向である状況の下で、行政書士が書類作成代理人として相手方と慰謝料をめぐる示談交渉を行い、和解契約書を作成する行為は合法的な業務といえるでしょう。
以上のとおり、当事者間に意見の対立がなく、争いもない状況の下では、行政書士が示談書の作成のために相手方とコミュニケーションをとることは、合法ですし、業務遂行には当然に必要な作業です。
また、行政書士が示談書を作成するのは、「権利義務に関する書類」の作成であり、当然に行政書士業務です。
仮に、相手方とコミュニケーションをとること全てがが弁護士法が規制する「交渉」であり、「非弁行為」であるとするならば、それはあまりに範囲が広く、行政書士という制度そのものが否定されることになるため、明確に誤っています。
5 まとめ
今回は、自称弁護士からの一本の電話を受けたことで、私見を記載しました。
開口一番、当事務所の業務が非弁行為であるなどの中傷されては、いい気持ちはしません。
当事務所の業務は、非弁行為に該当しないように常に注意を払っているほか、判例や政府解釈、行政書士会や行政庁の見解である「事件性必要説」を根拠としています。
当事務所は、自称弁護士からの電話に対しては、「交渉」の定義が不明確である以上、客観的な基準なしに非弁行為にあたると主張することは認められないと反論しました。また、そのような主張は書面でなされるよう申し入れました。
第一、弁護士のくせに、いきなり電話をかけて当事務所を中傷し、揺さぶりをかけようとするあたり、輩のような印象を受けます。行政書士業務の正当性や法的根拠、解釈に理解がないことは明らかです。
万一、書面が届いた場合でも、当事務所は、その業務の正当性については理論武装しており、降りかかる火の粉は払う次第です。
無用な争いは好みませんが、戦うべき時は徹底して戦うのが当事務所の方針です。