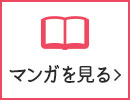民事訴訟では、原告と被告が主張を証拠に基づいて戦わせ、裁判官が法的に妥当な主張をしたものを勝利させる一種のゲームです。
そして、勝訴のためには、被告が自ら原告に権利があることを認める(認諾)か、裁判官に原告に法的な権利があることを確信させなければなりません。
当事務所では、これまでにも原告として、少額訴訟、通常訴訟(簡易裁判所、地方裁判所)の経験がありますが、相手方の反応については、重大な関心ごとです。
契約書がない場合でも、やり取りをメッセージとして残したうえで、相手から「支払います」というような発言があれば、被告としては、支払うことを約した(支払義務があることを認めた)と解されます。口頭でのやり取りでは証拠として残らないため、メールやチャットなどの文字に残すことがポイントです。
また、被告から「支払います」という発言がなかった場合でも、こちらが作成した書面に対する反応として「これでOKです」「これでお願いします」など返答があれば、それは被告は原告に業務を依頼したことを認めたことになりますので、少なくとも、原告と被告との間には何らかの委任契約があったものとみなされます。委任関係があることは、当然に報酬についても折り込み済みであると解されます。もっとも、委任契約は原則としては無償となっているため、訴状では、有償での委任契約であった旨を主張しておきます。
他にも、訴状に対して、被告が答弁書や準備書面を全く提出せず、口頭弁論期日にも出頭しない場合には、「擬制自白」が成立します。被告には、原告の主張に対して全く言い分がないとみなされ、原告の主張を全て認めたものと扱われます。その結果、原告は、実質的な審理なくして、原則として自動的に勝訴することになります。被告はいわゆる「欠席判決」となり、敗訴してしまいます。
そして、中には、契約自体は成立したが、その後に連絡がとれなくなり、こちらが作成した書面(成果物)に対して、全く返答がない場合も注意が必要です。
相手としては、何も主張しない=そもそも契約が成立したという認識がない、言い分が不明であることがあるため、この場合は、原告において契約が成立したことを主張・立証する必要があります。
対策としては、「○日までにご連絡がない場合は、この内容で承認いただいたものとみなします。」などのメッセージを残しておくことです。こうすることで、請求書と当該メッセージを合わせて、裁判官に契約の成立をアピールすることができます。
実務の面では、答弁書が提出されれば、必要な対応を講ずることができます。また、「支払います」などの言質があれば、証拠としては強いです。
問題なのは、答弁書も出さず、期日にも出頭しない場合です。
この場合、通常であれば擬制自白が成立し、原告勝訴となりますが、裁判官が契約の成立に疑問がある場合は、請求が棄却される場合があるようです。
契約書を作成することがセオリーですが、契約書がない場合でも、その後のやり取りを記録しておくことは必須です。
答弁書で原告の請求を認めてくれるのが一番ですが、それがない場合でも、言質を取っておくことで、契約の成立が認められ、支払請求が認められることが多いです。
当事務所では、これまでにも20件ほどの訴訟手続きを独力で対応しています。
ある程度の裁判知識は、行政書士を続けるうえで、リスク対策として必須でなはいでしょうか?